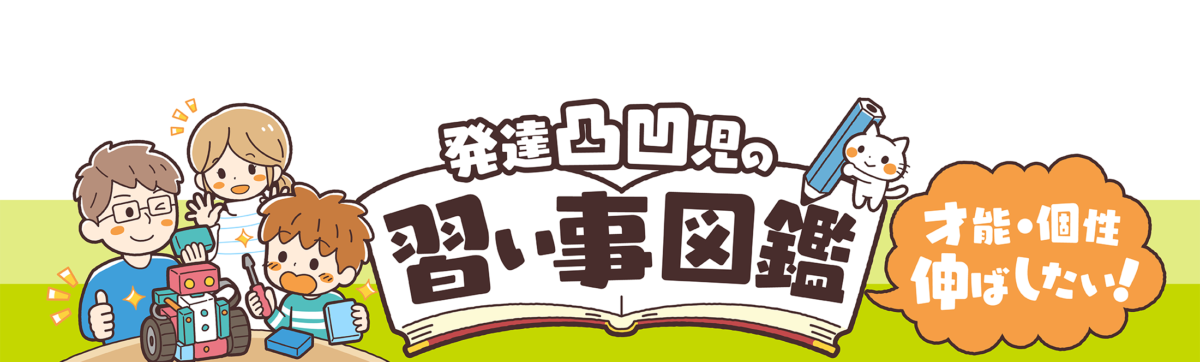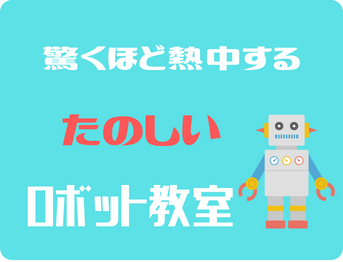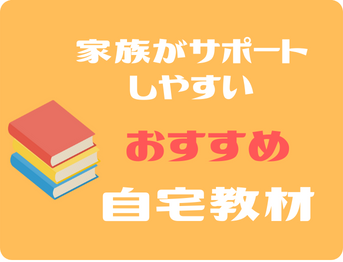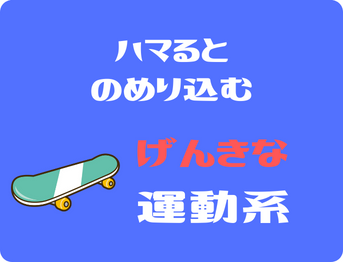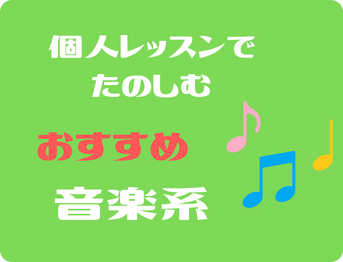発達に凸凹のある子の自己肯定感を高める習い事とは?
発達に凸凹あるお子さまや発達障害があるお子さまの子育てをしている中で、こんなことを考えたことはありませんか?
何か好きな事を見つけてあげたい!
得意なことを伸ばしてあげたい!
自信が持てることをつくってあげたい!
ありあまるエネルギーを発散してあげたい!
それと同時にこんな不安もあるかもしれません。
集中して取り組むことができるかな
始めてもすぐにやめてしまうんじゃないかな
お友達に迷惑をかけたらどうしよう
そもそも入会を断られたらどうしよう
自信を失ったらかわいそうだな
わが子のためにと思って通わせた習い事がかえってストレスになったり、自信を失うことにつながったらどうしようと思うとなかなか一歩がふみ出せないのではないでしょうか。
【発達凸凹児の習い事図鑑】では同じように不安を持ちながらも一歩を踏み出してお子さまを習い事の通わせた先輩パパ、ママ達の声もたくさん集め、お子さんにおすすめの習い事を紹介しています。
このサイトが発達に凸凹のあるお子さんの習い事探しの少しでも役に立ったら嬉しいです。
お子さんが発達障害に気づいた時期や行動は?
発達凸凹児や発達障害児の子育ての中で『はじめての子育てだから大変なのか、この子が特別手がかかるのか』と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか?
発達の凸凹に気づいた時期として多いのは
また、もしかして発達障害があるのかも?と感じた行動として多いのが
等です。 今は発達障害に関する情報を容易に手に入れることができます。 本やネット、SNS、YouTubeにも発達障害をカミングアウトしている方の動画がたくさんアップされています。 この特性はうちの子に当てはまる、当てはまらない。 うちの子は発達障害とは違う、いやそうかもしれない・・色々な葛藤があったかもしれません。 育児に追われ毎日ヘトヘトな現状の中でゆっくりと悩んでる暇もなく、しっかりと向き合って考える時間もありません。 パパやママはあわただしく発達凸凹児の子育てをしながら 『あんなに怒らなくてもよかったかな』 反省をしたり、うつな気分になったり、時には孤独を感じることもあったのではないでしょうか。 そんな自分たちの感情からお子さんの生きづらさに気づく方も多いようです。 『あんなに怒らなくてもよかったな』➡うちの子は怒られることが多い 『癇癪が心配で家にこもりがち』➡家の中ばかりでパワーを発散できない 『居場所がない・・』➡うちの子も居場所が欲しいかもしれない お子さんが褒められる機会が少なく自己肯定感が下がってしまったり、コミュケーションがうまくとれないことで自分では思っていないようなトラブルを起こしているのであれば、親として何かできることはないか考えたいですよね。 発達障害に関する情報の中には 「発達障害児は、注意されすぎることが多く自己肯定感が低くなりがちです。好きなこと、得意なことを伸ばしてあげましょう」 と書かれていることも多く、目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 体を動かすのが好きな子、絵を描くのが好きな子など、すでに得意なことを見つけているお子さんには、それを伸ばす環境を整えてあげやすいかもしれません。 ですが、どちらかというと不得意なことばかり目について、得意そうなことが今は見当たらない・・そんなお子さんも多いかもしれません。 そのような場合には、色々な習い事の体験教室に参加してみましょう。 習い事との相性だけでなく、先生との相性も大事です。『体験あり』と特に宣伝しているところでなくても、事情を話して体験をお願いしてみると受け入れてくれるところも多いですので、お子さんのためと思って勇気を出してお願いしてみましょう。 手当たり次第に体験をするのは、新しい場所や人になじみにくいお子さんの場合、ストレスにもなりますので下の5つのことに気をつけて選びましょう。 特性に合っていること

わが子の発達障害を受容するまでの葛藤
『外で癇癪をおこされたら困るからもう出かけたくない・・』
『いつもどこでも謝ってばかりで居場所がないや・・』等発達の凸凹のあるお子さんの生きづらさに気づく
発達凸凹児(発達障害、グレーゾーン)に向いている習い事は?
発達凸凹(発達障害)児の習い事選びで気をつけたい5つのこと
発達の凸凹や発達障害のあるお子さんは、集団での取り組みや協調することが苦手な子が多いかと思います。
人が多くて集中できなかったり、音に敏感だったり、先の見通しができなかったり。
お子さんの苦手なことしっかりと見極めることが大事です。
興味関心を持っていること
興味のない習い事は子どもにとってはストレスとなりプラスになることはありません。
うたが好き、絵をかくのが好き、体を動かすのが好き!
好きで興味のあることならストレスなく習い事ができますよね。
凹の矯正のための習い事はNG!
それとは逆に苦手な嫌いなことをどうにか克服させようとして始める習い事は続かないようです。
運動が苦手だから体操教室へ。リズム感がないからリトミックへ。不器用だから工作教室へ。
普通のお子さんなら苦手克服が目的で習い事をするのも良いかも知れません。
が、それでなくても幼稚園や学校、療育などで苦手なことにもチャレンジしている凸凹児。習い事まで苦手なことだったら自己肯定感も下がってしまいます。
もし、苦手なことを少しでも克服をして自信をつけさせてあげたいといった場合は個人レッスン(個別授業)で、お子さんのペースでできるところがおすすめです。
お子さんにとって楽しい時間になるような習い事を選びましょう!
発達障害に理解のある教室で!
楽しい時間になる要素には、指導者の理解がとても大きいと思います。
パパやママでも付き合いきれなくなるような一方的な話や、なかなかおさまらない癇癪にも根気強く寄り添ってくださる先生もいらっしゃいます。
また、先生にご配慮いただけるという点ではやはり集団で行う習い事よりも、個人で行うもの(ピアノ、習字、絵画)やチームプレーではない運動(陸上、水泳や武道)、集団授業ではないタイプのロボット教室やプログラミング教室などが良いでしょう。
習い事をスタートする時期
習い事を始める時期によっても向き不向きが変わってきます。
未就学児の頃は衝動性が強く出ていたお子さんでも年齢とともに落ち着いてくる場合もあります。また、成長とともに言葉の理解度や社会性が上がり、グループ活動も苦にならなくなる場合もあります。
習い事のスタートの時期を見極めること大事です。
発達障害の子の特性をしっかりと理解しよう
発達に凸凹(障害)がある子どもには様々な特性があります。
その特性としっかり向き合うことはとても大切ですが、苦手の克服に重きをおいた習い事選びをすると集団での活動になかなかなじめないなど、苦労することもあるでしょう。
また発達凸凹児の場合、一つのことに集中できなかったり、興味がないことにはまるでやる気おきないこともあります。
その代わり、打ち込めることを見つけると、持ち前の集中力によって類まれなる才能を発揮する場合もあります。
習い事選びには、その発達の凸凹の特性を活かせること、その特性により習い事がストレスとならないことが大切です。
まずは子どもの特性についてしっかりと把握することが必要です。
発達凸凹(障害)の特性 まとめ
発達凸凹・発達障害・グレーゾーン児におすすめの習い事!
発達に凸凹があるため、集団で行動することが多かったり、見通しの立ちにくい習い事は向いていないかもしれません。
向いている習い事として考えられるのは「チームプレーなどの多くのコミュニケーションを求められないもの」だと思います。
また1つの物事に集中できるという特性をいかして書道や絵画、ロボット教室、プログラミング教室など自分のペースでコツコツと続けることのできる習い事も向いていると思います。
音楽教室も個人レッスンで、さらに発達障害に理解のある先生であれば、長く続けられる習い事なり、実際に楽器演奏を得意なこととして実際に楽しんでいる子も多いです。

こちらの本の著者、中嶋恵美子先生のHPでは以下のように書かれています。
私たちにとっては当たり前のことでも、発達障碍の方々にとっては当たり前ではないことがたくさんあります。
発達障碍の方々は、私たちの視点に自分たちを合わせようと一生懸命努力してくれています。しかし、私たちが彼らの視点に歩み寄ることも大切なのではと感じます。お互いの歩み寄りによって、信頼関係は築き上げられるものですし、音楽のあるレッスン風景にはそんな歩み寄りが似合います。
こんな先生のもとでレッスンしたいですよね。現在、新規の生徒さんは募集していないようですが、発達凸凹児を受け入れているピアノ教室の紹介がありましたので、ご紹介しておきますね。
「ギフテッド」と発達凸凹(発達障害、グレーゾーン等)
「ギフテッド・チルドレン」や「才能はみだしっ子」という言葉を聞いたことがありますか?

「天から与えられた能力」という意味で、知能指数が非常に高い子どもや、 スポーツ、音楽、美術などに特異な才能をもつ子どものことをギフテッドと呼び、アメリカでは3~5%の子どもがギフテッドではないかと考えられています。
相対性理論の唱えたアインシュタインや19歳にしてFacebookを起業したマーク・ザッカーバーグ、アップルを創ったスティーブ・ジョブズなどもギフテッドと言われています。
その高い能力によって行動や思考に一般の子どもとは違う特徴があるといわれ、そうした行動の一部がADHDの子どもが示す特徴と似ているために、 ADHDやそのほかの障害があると間違われてしまうことも多いことがわかっています。
なかにはギフテッドとADHDのどちらの特性も持ちマイナス面が目立つため、ギフテッドの能力に気づかれない場合もあります。
たとえば、学校での授業内容が本人にとってあまりにも簡単すぎるため身が入らずに集中できなかったり、教師に反論したりすることが多く、こういった態度や行動が「不注意」や「反抗」 などとみなされ、 ADHDと診断されることがあるのです。
知能指数が高いADHDの子どもは、「ギフテッド」で ある可能性も考慮し、きちんと見極めることも重要です。
NHK クローズアップ現代 2019年8月28日 知られざる天才 “ギフテッド”の素顔
しかし、習い事の目的はギフテッド探しではありません。
発達に凸凹のある子どもに対し、過度な期待を押し付け、習い事を居心地の悪い場所にしてしまうのでは本末転倒です。
あくまでも子ども本人が興味があってを楽しみながら続けられることが大切です。
その結果、日ごろ注意を受けることの多い発達に凸凹のある子どもの強みとなり、自信につながるといいなと思います。